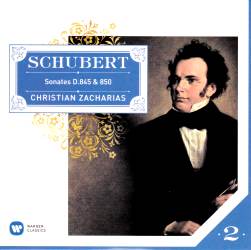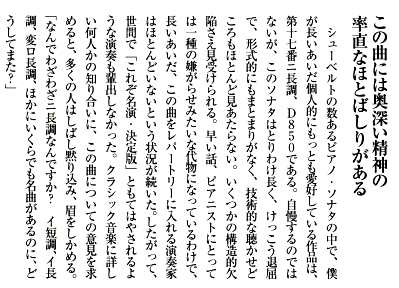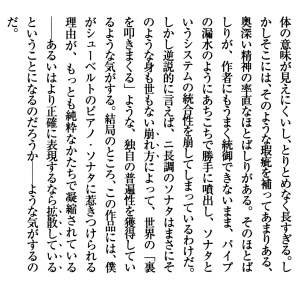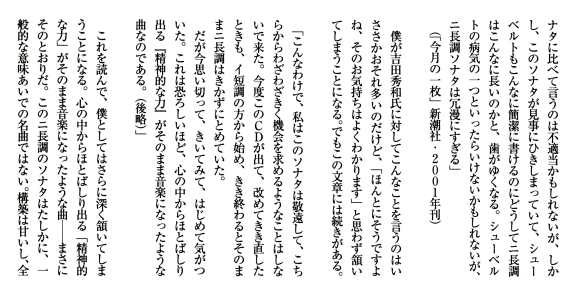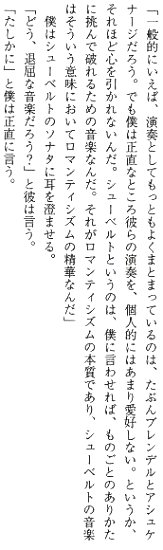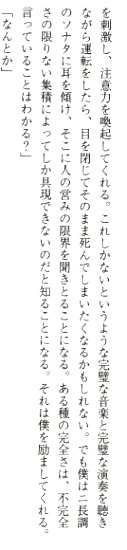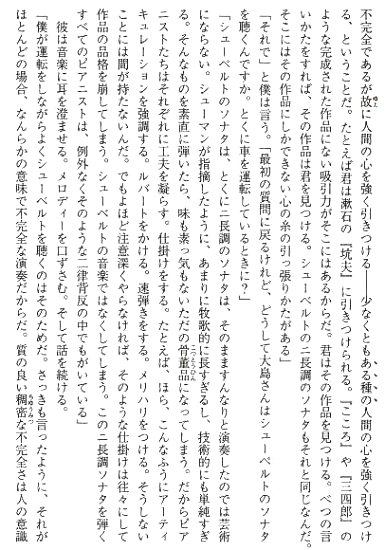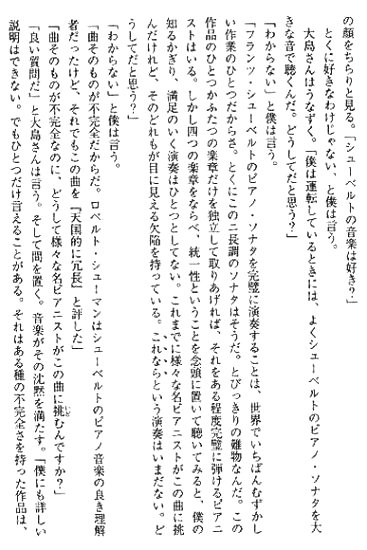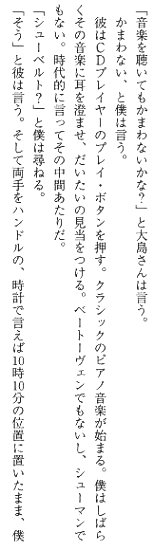|
 |
 |
 |
 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clifford Curzon (1907 -
1982) Recorded June 1963 |
Walter Klien (1928 -
1991) Recorded 1971-1973 |
Eugene Istomin (1925 - 2003) Recorded : June/September 1969 |
Leif Obve Andsnes ( 1970
~ ) Recorded : October 2002 |
|||