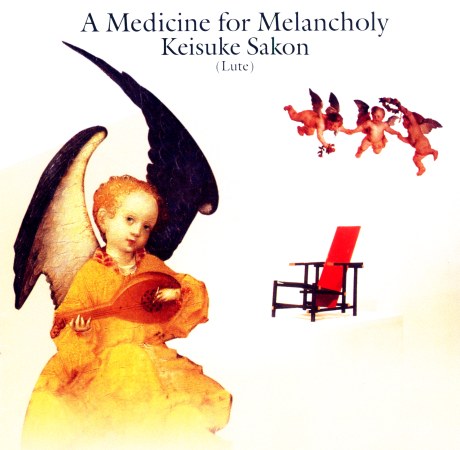 |
 |
美しきもの見し人は
メランコリーの妙薬
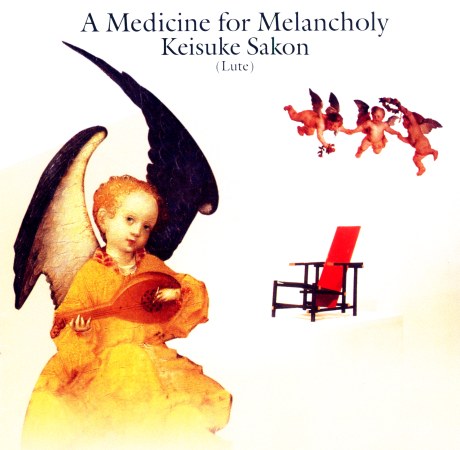 |
 |
 |
リュートという楽器はササン朝ペルシア (AD226-651) 頃に現れ、その後アラビアを経てヨーロッパに伝わった。
リュートの名はアラビア語で “木” を意味する (” al ’ud アル - ウード ” )に由来する。
8世紀にイベリア半島に侵入したアラブ人が持ち込んだ、あるいは11世紀頃にパレスチナに侵入した十字軍が持ち帰った、等々諸説がありますが、古くからヨーロッパにもたらされたことは確かだ。
さらにシルクロードを経由して中国やインドにもたらされ、アジア各地で様々な楽器へと発展し、日本では琵琶となった、等々、世界に広まった。
和音も旋律も弾ける万能性から、とりわけヨーロッパでは14世紀から16世紀のルネサンスからバロック時代に全盛を極め、独奏楽器、歌の伴奏、宗教音楽の通奏低音等、広範な用途に用いられた。
そして音楽が多様化するに従い、音域を広げるために弦の数が当初の4コースから次第に増え、ルネサンス時代には 6~8コース、バロック時代には11~13コースへ、さらに低音域を伸ばした大型のテオルボ(アーチリュート)では14コースへと拡大された。
ルネサンスリュートは第一コース以外の弦は共鳴する複弦が張られ、このため独特のふくよかな音色が奏でられる。
と、ヨーロッパ全土で300年余に余り全盛時代を誇り、今日のギターやピアノ同様に庶民から、プロ音楽家に至るまで絶大な人気を博した楽器だった。
イギリスのエリザベス一世時代は女王自らがリュートを演奏し、4人のリュート奏者を召し抱えて、毎朝健康のために彼らの演奏舞曲を踊ったという逸話まであるほど。
そのため、ジョン・ダウランド、トーマス・ロビンソン等の作曲家が多数輩出し、彼らが作曲、あるいは編曲した、”涙のパヴァーヌ”、”グリーン・スリーブス” 等の曲は今日に至るまで広く演奏されている。
バロック音楽時代の終焉とともに、リュートは急速に衰えていった ; 音量が小さいこと、ガットという温度や湿度に敏感な弦が多数あり、調弦が余りにも大変で時間がかかるため、他の楽器との合奏に困難が生じた等、いくつかの要因があったためだ。
リュートの楽譜 : タブラチュア
16世紀のリュート曲のタブラチュア譜(上、下段)と、5線譜(中段)の比較
リュートについて述べる場合、楽譜がタブラチュア(奏法譜)という、5線譜とは異なる方法で書かれていることを述べなければならない。
今日、広範に使われている5線譜は、17世紀イタリアでオペラのために完成されたが、それまでに紀元前3世紀にギリシアで書かれた ”アポロ賛歌” の5線ならぬ1線のみのごく単純な記述から2000年近い、様々な試みを経て、音の高低、長さ等を記述しようという試みの歴史があったわけだ。
リュートのタブラチュアという楽譜は、どの弦のどの位置を抑えるかという記述法で、これはギター、ハーモニカ、さらには日本の琴、三味線、尺八等も含め、世界の様々な楽器に使われている楽譜の記述法だ。
リュートの場合、最大では14コースにも拡大された弦の低音部の弦は指で抑える必要はなく、音域の拡大のために追加された開放弦がただ一つの音域を受け持つだけの役割を果たす。
ただし追加された弦は調弦の必要があり、しかも第1コース以外の弦は共鳴のための複弦となっているから、それぞれを正しく調弦するのは大変な手間と時間がかかる(80年生きたリュート奏者は、その生涯の60年を調弦に費やした)と言われるほど。 これがリュート衰退の原因の一つだ。
リュート奏者、左近径介の生涯
冒頭のCDはルネサンスからバロック時代に至る、ヨーロッパ各地で作曲されたリュート曲を、大型のリュートであるキタローネと3台のルネサンスリュートと1台のバロックリュートの5種のリュートで演奏したもの。
3世紀にわたってヨーロッパ各地で作曲されたリュート曲を演奏するためには、それぞれ音域の異なる様々な楽器を使わなければならない。
演奏者は、2009年に60歳にならずして悪性のリンパ肉腫であっという間に死んでしまった我が弟で、このCDは弟が1993年に録音してCDとして残した唯一のもの。
”メランコリーの妙薬” とはブラッドベリが書いた短編の表題だが、エリザベス朝時代イギリスのリュート奏者のトーマス・ロビンソンが作曲した ”メリー・メランコリー” が録音されているので、ブラッドベリの短編の題にかけてタイトルとしたということ。
弟が音楽に興味を抱いたのは、中学生のころ、ラジオで放送されたバッハの無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番のシャコンヌをアンドレス・セゴビアがギターに編曲した曲だった。
セゴビアはチェロのパウ・カザルスと並び、それまで忘れられていたバッハの再発見に多大な功績のあった演奏家だが、現在の奏者は、セゴビアやカザルスのようなロマンチックなスタイルでの演奏は決してしない。
セゴビアのバッハは、いわばセゴビア節ともいうべき個性の強いものだが、しかしバッハの曲はクラシックでありながらモダーン・ジャズであれ、ロックであれ、サンバであれ、如何なるスタイルで演奏しようが紛れもなくバッハに聴こえるという不思議な力を秘めている。
とりわけセゴビアの演奏には麻薬のような吸引力があり、わが弟はその、魔力に憑りつかれて、ギターを入手し、独学でバッハを弾こうと思い立ったというわけ。
その後音楽とは全く関係ない大学に入学したが、中退してイスラエルにわたり集団農場のキブツで働いた後、ヨーロッパ各地を訪れて、たまたまドイツのケルンで立ち寄った楽器店にて展示されていたギターを弾かせてもらった。
その場に居合わせたドイツ人が実はケルン音楽大学に新設されたギター科の教授で、弟の演奏を聴いて、入学を勧誘したというのが、弟が正式に音楽の道に入る発端となった。
そんなに簡単に音楽大学に入学できるのかと思いますが、ヨーロッパではある程度の水準があれば入学は出来るというのが、日本とは天と地ほどに異なる。
ただし、日本との違いは、入学は簡単でも卒業は至難の業だ。
とりわけ歴史的にマイスター制度を基本に社会が成立してきたドイツでは、何をするにしてもマイスター制度に基づく国家資格が無いと、仕事に就くことが出来ない。
音楽の道も同様で、演奏技術と音楽性とが厳しく選別され、卒業するのは簡単ではない ;
卒業試験で最優秀ディプロマの資格を得たものだけが独奏者として舞台に立てる。
普通のディプロマでは独奏者にはなれないが合奏者の一員としてなら認めらる。
さらに、プロの演奏家にはなれないが、音楽教師としてのディプロマがある、と厳格な位置づけが行われる。
そして、いずれのディプロマも得られない場合はプロの音楽家としての道を断たれ、個人の趣味として続けなさいと宣言される、というのがドイツの、恐らくは他のヨーロッパの国々でも同様のクラシックの世界の音楽事情なのです。
日本のように、音楽で声楽を学んだが、ピアノも少し弾けるから、需要の多いピアノ教師としてやって行けるということは決してあり得ない。
さて、そうして音楽大学に入学したものの、独学で名曲の触りだけをつま弾いていたのみ、基本的な音楽の知識も演奏技術も無かったわけで、徹底的に初歩から鍛え直され、ともあれわが弟はギター科の最初の卒業生として最優秀ディプロマを得て卒業できた。
とは言え、ギター奏者など世界にゴマンといるわけで、卒業したからといってギターの世界で生きてゆくことは容易ではない、というより、子供のころからきちんと教育を受け、音楽性も演奏技術も遥かに高い世界のギタリストに伍して生きてゆくのは不可能だと、わが弟は自覚していた。
さらに、ギター音楽の世界は、ラテン系の作曲家が大半で、レパートリーが少なく、クラシック音楽の世界ではいささか異端に属し、ラテン系生来のリズム感が身についていない東洋人が対抗してゆくのはほぼ不可能、と自分の実力をしっかりと自覚していた。
そこで、当時復活しつつあった、ヨーロッパ各国で300年の歴史を持ち、膨大な曲が埋もれているリュートの世界なら、ドイツで正規の音楽教育を受け、ヨーロッパの音楽の本質を理解している自分でもやってゆけると、新たにリュート科に入学した。
バロック時代末期以降、すっかり忘れられていたリュートという楽器を復活させたのはドイツのワルター・ゲルヴィッヒ (Walter Gervig : 1899-1966) であり、その高弟がケルン音楽大学のミヒャエル・シェファー (Michael Schäffer : 1956-1996) とスイス、バーゼル・スコラ・カントルムのオイゲン・ミュラー-ドンボワ ( Eugen Müller Dombois :1931 - 2014) だった。
当時のケルン音楽大学は、ミヒャエル・シェファーとその一番弟子のコンラート・ユングヘネル(Konrad Junghänel : 1953~)を中心に、ヨーロッパでのリュートの復活の一大拠点であったから、ギターの後でリュートを学ぶには絶好の場所だった。
無事にリュート科も卒業したのだが、モーツァルトでさえ野垂れ死にしてしまったのがクラシック音楽の世界だ、 時代が変わったとはいえ、音楽の世界で生きてゆくのは容易なことではない。
まして、リュートという、殆どの人が見たことも聴いたこともない楽器ではなおさらのこと、演奏会を開いても小さな会場に殆ど客が来ないような日も少なからずあった。
しかしながら、如何に苦しかろうと、金にもならなかろうと、演奏技術を磨き、レパートリーを拡大し続けるためにも、定期的に演奏会を開催することが必須の条件なのだ、とは弟の弁で、それは間違いないだろう。
ゴルフだってレッスンプロでは如何に上手くとも、公式の試合で切磋琢磨して勝ち抜かなければプロとして生き残れない。
が、現実は演奏会のたびに少なからず赤字となるというのがクラシック音楽の世界だ。
ただ、アマチュアのコーラス団体が主催する演奏会には大いに助けられた。
アマチュアとは言え、本格的に演奏会を目指すとなれば1年がかりで練習を重ねてルネサンスやバロックの合唱曲を披露するとなれば、伴奏はピアノやオーケストラではなくクラヴサンやリュートといったオリジナ楽器でなければと、弟とケルンの音楽大学でピアノとクラヴサンを学んだ弟の妻とにお呼びがかかったのだ。
彼らにとっても、ヨーロッパで学んだ専門家が楽器持参で伴奏してくれるのは願ってもない機会なのだ。
自分の演奏会であれば、赤字必至にも拘らず、ポスターや会場の様々な準備等、何から何まで自分で手配しなければならないが、アマチュアの演奏会の伴奏は、前もって準備した曲をリハーサルと本番とで演奏するのみ、そのうえで望外な謝礼を払ってもらえるとなれば、長年の音楽家生活で唯一、音楽を安心して楽しみながら演奏できる数少ない機会だった。
ピアノやヴァイオリン、フルート等々、なじみのある楽器の演奏家でも、例えば日本で、演奏会やCDの売り上げだけで食べて行けるのは片手の指くらいとはよく言われる。
それに加えて、楽器の維持費も馬鹿にならない ; ルネサンスからバロックに及ぶ300年の歴史があるリュートは膨大な曲が作曲され、演奏され、それに伴う楽器の発展で大きさや音程の異なるタイプが出現してきた。
冒頭のイギリス、フランス、ドイツ、イタリアの曲を演奏するだけでも5台の異なるリュートが必要となる。
そしてそれに必要な羊の腸の弦の数たるや100本を超える。
弦は消耗品だから、常に新品を備えなければならない。
さらに新しい曲を演奏するためには楽譜が必要だが、タブラチュア譜という特殊な楽譜は全て輸入品しかないから、弦と共に楽譜を揃えるにも莫大な費用が掛かる・・・・・・
と、リュート奏者がどうやって生活して行けるのか? 想像することも出来ない。
安定した収入があるサラリーマンが羨ましいとは弟の口癖であった。
他に潰しが利かないから已むを得ずサラリーマンをしているだけで、本当は好きなことをして生きて行ければそれに越したことはないが、しかしサラリーマン生活だって傍目に見るほど気楽なものではない、と言ったところで音楽家としての生活しか知らない弟には決して理解できないだろう。
冒頭のCDはそんな弟が唯一残したものだ。
ソニー・レコードにて当時は最新の20ビットのデジタル録音し、発売されたものだが、しかし録音費用等々を自ら負担した、殆ど自費出版に近いものだ。
NHKのラジオやテレビ番組に時折出演していたとは言え、放送が終われば、記憶から薄れてしまう音楽を、レコードという形で残したいと考えてのCDだったが、単なる自費出版では、自己満足に終わるのみ、大手のレコード会社での録音出版と販売網にて世の中に残せるという思いで録音したのが、唯一の形見として残った。